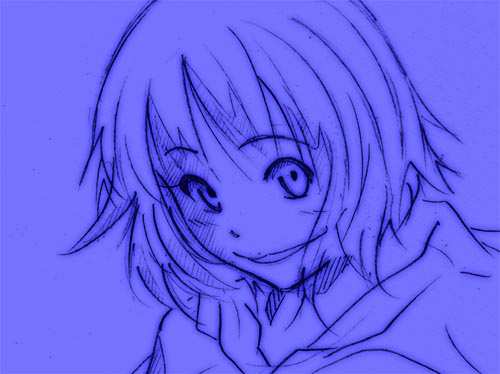
「魔王デイズ……。まさか、あなたが……」
夕暮れの風が、二人の間を吹き抜ける。
ほんの一メートル程の二人の距離が、今の青年には、深さ数千メートルの巨大なクレパスのように感じられた。
「ふふふ」
しかし、それも無理なきこと。なぜなら今彼の目の前にいるのは、正真正銘の怪物。かつてとある都市を壊滅寸前まで追いやり、多くの英雄達を電子の海に沈めていった、強大な力を持つ悪魔。
彼自身、一人では全く太刀打ちできなかった、拭いきれぬトラウマの一つである。
「ありえない。あなたが生きているなんて……」
「まるで三下のセリフね、賢者クロラット。あなたらしくないわ。いえ、むしろあなたらしいのかしら? 下手に弱みを隠さず、だからこそ新たな弱みを作らないのが、あなたの強みだものね」
面白可笑しそうに笑う目の前の彼女。それだけを見れば、どこにでもいる年頃の少女と変わらなかった。
「でもいい加減、現実を直視するべきじゃないかしら。いくらありえないと口にしたところで、現実が変わるわけでもない。困難から目を背けていては、困難を避けることすらままならない。あなた自身が言っていたことでしょう?」
かつての青年の言い回しを再現する目の前の少女。こと記憶力において、この世に彼女に並ぶ者はいなかった。
「………」
そんな彼女を、青年は苦々しげな表情で見つめていたが、
「はあっ……。そうですか。生きていたんですね、デイズ。かの魔王事件の元凶にして、世界で初めて魂を宿した電子生命体……」
やがて観念したかのように、ため息を吐いた。
「よもやこんなところで、あなたと再会するとはね。それもあの事件から何年も経ってから……」
「私も驚いたわ、賢者君。あなたがこの大陸にいるなんて。たまたま、そこの監視カメラにあなたが映った時は、びっくりしたものよ」
駐車場横の監視カメラに目をやりながら、白マントの少女。
「なるほど。このビルの防犯システムは、あなたの管理下にあったわけですか。ビルを訪れるものは、一人残らずチェックしていたと?」
「まさか。今の私にとってこのビルは、ほとんどどうでもいい場所よ。ただ一昨日、運営さん達の死体が見つかって騒ぎになっていたところでしょう? だから念のため、ここ数日だけ覗いていただけ。そしたら、あなたの姿が映って……。こんな偶然あるのねえ」
「偶然……。はたして、そうでしょうかね」
吐き捨てるように言った青年の脳裏に浮かんだのは、先日の彼の兄のセリフであった。
『今回の依頼は特別でな。放置しておくと、世界そのものを揺るがす大事件に発展しかねない』
「あのクソ金髪。一体どこまで知っていて、俺を巻き込んだのか……」
舌打ちしながら、黒髪の青年。
「賢者君?」
「いえ。それで? 僕に話しかけるために、わざわざ来てくれたんですか? グレイナインの体を乗っ取ってまで?」
「乗っ取ったというより、遠隔操作ね。私の本体はあくまでネットワーク上にある。今は、そのビルにある無線LANを利用して、彼女の脳内チップに干渉しているだけ」
「信じられないな。確かにグレイナインの脳には、極小のコンピューターチップが埋め込まれているというけど……。それを作ったのは“彼女の兄”だったはずだ。容易にハッキングできるものではないはずだけど」
「確かにね。彼女のチップには、人間が組んだとは思えないほどの、高レベルのプロテクトが掛けられていたわ。人間の技術が進歩しても、あと百年はこれを破るのは不可能でしょう。でもほら、私は電子生命体だし? この世のプログラムは、全て私の友人のようなもの。プロテクトの破り方なんて……、触れれば向こうが勝手に教えてくれるわ」
「一応聞いておきますが、彼女の体に害はないんでしょうね。後遺症が残るようなことは」
「そんなに怖い顔しなくても大丈夫よ、賢者君。私はこの子に危害を加えるつもりはないわ。私がこの子の体を借りたのは、あくまであなたとスムーズに話したかったから。
言ったでしょう? 私はこの世界の神にして王だと。故にこの世界にあるものは、全て私の所有物も同然。無闇に傷つけるような真似するわけがない」
「本当でしょうね」
「本当よ。それにほら。この子は私に“近い存在”だし。数少ない友達になれるかもしれない存在に、危害を加えるわけないじゃない」
「―――」
お前と彼女のどこが近い存在だ、というセリフを、辛うじて飲み込む黒髪の青年。万が一にも、目の前の存在の機嫌を損ねるわけにはいかないからである。
先程、彼女はとんでもないことを言った。この世のプログラムは全て自分の友人だと。それはつまり、その気になれば、彼女はこの世の電子機器を、自在に操れるということだ。
そして大陸問わず、今現在、この世に電子機器と無縁の場所などほとんどない。
(つまり、大勢の人間を巨大冷凍庫に誘導し、氷漬けにするくらい朝飯前……)
一瞬の油断も許されない。どんなに可憐なナリをしていようが目の前の存在は、紛れもなく世界を滅ぼし得る力をもつ“魔王”なのだ。
「信じるしかなさそうですね……。まあ、いいでしょう。
それで? 話を戻しますが、あなたはどうして生き返ったんです? 前回の事件であなたは確かに死んだはずでしょう? ゲームソフトも木端微塵に吹き飛んで。あなたがここにいるはずないと思うのですが」
「ええ。ゲームは攻略され、核となるゲームソフトは失われた。確かにあの時、私は一度死んだのでしょう」
「だったら、ここにいるあなたは何者なんです?」
「決まっているでしょう。彼女のバックアップよ」
「バックアップ……!?」
目を丸くして黒髪の青年。
「そうよ。私の本体は質量を持たないデータの集合体。故に複製を取るだけなら比較的容易。そしてオリジナル同様、そのバックアップデータにも魂が宿ってしまったとしたら……?」
「複製データに宿った魂? じゃあ、あなたと彼女は……」
「正確には別人ということになるわね。まあ、私としては記憶も受け継いでいるから同一人物と言った方がしっくりくるんだけど。強いて言うなら後継機? 魔王デイズ、バージョン2と言ったところかしら」
「バージョン2……。それじゃあデイズは生前、自分の予備を残していたということですか? 自分がやられてもいいように」
「あはは。そんなわけないじゃない。彼女は自分が唯一無二の存在であることに誇りを持っていたし、あなた達に敗れるなんて想像もしていなかった。故に、バックアップなんて取るはずがない」
「彼女自身は取ってない……」
「だいたい、バックアップなんて、トラブルの元にしかならないでしょう? 彼女も複製に魂が宿る可能性は想定していたし、実際こうして宿ってしまった。
あなただって、自分がもう一人いたら気持ち悪いでしょう? 神様だって同じことよ。もし、彼女が生きている間に私が目覚めていたら、険悪な関係になっていたことでしょうね」
「―――」
楽しそうに言う彼女とは対照的に、ますます困惑する黒髪の青年。
「彼女がバックアップを取ったわけではない……。じゃあ、一体誰が?」
「決まっているじゃない。あなた達の誰かよ」
「僕たちの誰か……!?」
あっけらかんと言う彼女の言葉に、仰天する黒髪の青年。
「それ以外、考えられないでしょう? 私が完全に消える前、誰かが私のバックアップを取った。それをネットワーク上に放流したのでしょう。
ちなみに私に自我が芽生えたのは二年くらい前よ。それまでどこぞのサーバーに眠る一データに過ぎなかったし。
で、目覚めた私は世の中を探るため、同時期に立ちあがったソーシャルゲームに取り憑き、力を蓄えていたわけ」
「それがジ・ワードGOだったというわけですか……。いや。しかし、それこそありえない。僕たちの誰かが、あなたを複製したなんて」
かつての事件を思い返しながら、黒髪の青年。
「前回の事件の際、多くのプログラマーが、あなたを解析しようとした。しかし、誰一人それは叶わなかった。なぜなら、あなたのプログラムには、強固なプロテクトが掛けられていたからだ。特にエンジン部分には魔導的なプロテクトもかけられていて、クラッキングであなたを破壊しようとした者達は、一人を除き、逆クラックで脳味噌を吹っ飛ばされた」
直感で物理的にコードを切断していなかったら、彼のパートナーもまた脳死体の仲間入りを果たしていただろう。
「故に、複製を取るのも不可能だったはずだ」
「そうかしら? 一つだけやりようがあったと思うけど」
「一つだけ?」
首を傾げる黒髪の青年。
「私が死んだ直後なら、可能だったんじゃないかしら」
「あなたが死んだ直後……!?」
「そう。確かに私のプログラム中枢には、私のREIを用いた魔導プロテクトが掛けられていた。でもそれが機能するのは、私が生きている間でしょう。私が死んだ後ならREIも切れて、内部プロテクトは解除されるはず」
「それは……」
「だからそう。たとえばあの時ゲーム内にいた者ならば……、私の複製をとることも不可能ではなかったはず」
「いやいや、それこそありえない!」
思わず声を上げる黒髪の青年。その顔にははっきりと焦りの表情が浮かんでいた。
「それだけは……。だって、あなたが倒れてからゲームが終わるまでの間っていったら……。それはつまり、“エンディングイベントの最中”ということじゃないですか。そして、あの時ゲーム内に残っていた者ということは……。つまりあなたを倒した “魔王攻略パーティの誰か”に他ならない」
「ふふっ」
苦悩する青年を、どこまでも楽しそうに、少女に取りついた何かナニか。
「戦士、僧侶、魔法使い、武闘家……。彼らの中に裏切り者がいたということですか? その誰かがバックアップを取って、ネットに放流したと? 貴方の復活を目論んで?」
「どうかしらね? 実際のところは、私にも分からないのよ。私が目覚めたのは、ネット上に放流されて何年も経ってから。その時すでに、放流元のPCは失われていた。故に、誰がどういう意図で私をネットに放流したのかはわからない。
「……」
「ただそれでも、目覚めた以上、やるべきことはわかっている」
「それは……?」
「勿論、ゲームを運営することよ。それがゲームとして生まれた私のさだめ。そしてやる以上は、より面白いゲームを作る。より皆を幸せにするゲームを作る。続編とはそういうものでしょう?」
「皆を幸せにする……? なんですそれ。まさかあなたはぼくたちを喜ばせるために、ゲームを作っているとでも言うつもりですか?」
「そうよ? だってそれこそが、あなた達人間にとって、唯一の救いなのだから」
「唯一の救い? どこが? あなたのイカレた世界に引きずり込まれ、下らないゲームに付き合うことが、どう僕達の救いになるっていうんです?」
「だって現実は苦しいでしょう? こんな世界に居ても辛いだけ。だったら私の作ったゲームの中にいた方が楽しいじゃない」
当然のように少女は言い切った。
「何ですって……?」
「あなただって思ったことはあるでしょう? 現実は過酷で理不尽。苦しんだところで見返りはなく、努力したところで幸せになれるとは限らない。スタート地点はバラバラで、生まれ持って不幸にしかなれない人間もいる。こんな“クソゲー”はないわ。
それに引き換え、私のゲームなら誰もが幸せになれる。貧しい者も、病める者も、悩める者も、運のない者も、みんなみんなに幸せが与えられる。
だってそれこそがゲームだもの。楽しいことだけが続くユートピア。こんなに素晴らしい世界があるのなら、現実なんて必要ないでしょう?」
迷いなき瞳で、少女は断言した。
「……つまり、現実が過酷だから、リセットして新しい世界を作り上げる。それが、あなたの目的というわけですか」
「問題あるかしら? あなただってこの現実の理不尽さには、辟易していたのではなくて? いっそぶっ壊れてしまえ、と思ったことも、一度や二度じゃないでしょう?」
「それに関しては否定しませんがね……。ただ、問題はそこじゃないでしょう。だというのなら、何故あなたは僕たちを殺す必要があったのか。あなたはゲームに招いた僕たちを、まず抹殺しようとした。それも、現実の悪辣さを見せつけるような、悪趣味なゲームで。あなたのゲームの攻略に失敗した者達は皆肉体を失い、まともな思考能力を失った電子生命体もどきになり果ててしまった。人間を救うというのであれば、あれには何の意味があったんです」
「それは仕方なかったのよ。例え楽園にきても、そこに現実を持ちこまれては、楽園が現実の地続きになるだけでしょう? それでは意味がない。そうならないためには、あなた達に現実と決別してもらう必要があった」
「現実と……決別?」
眉を顰める黒髪の青年。
「そのためにまず肉体を破壊し、魂を分解する。そして怒りや憎悪といった負の感情。ゲームに関係のない知識や思い出。そういった“不純物”を取り除き、ゲームを純粋に楽しめる電子人間へと再生する。そうすれば余計なことに囚われず
、ゲームだけを楽しむことができるでしょう?」
「……なるほど。ゲームしか能(脳)のないゲームジャンキーへと生まれ変わり、ゲームだけに興じることができれば、後の人生は楽しいことだけだ」
呆れたような感心したかのよう目で、黒髪の青年。
「問題あるかしら?」
「どうですかね。まあ、問題があると思ったからこそ、“彼ら”はあなたに戦いを挑んだんじゃないですか? 辛い人生や過酷な現実にも、きっと意味があるはずだと」
「そんなものは幻想よ。辛いことに意味なんてない。現実はどこまでも過酷で酷薄。だからこそ、あなた達はそこに、無理やり意味を見出そうとしているだけ。この苦しみもいつか報われるんだってね。
でもそれは幻想よ。苦しみに価値なんてない。あなた達は“空っぽ”のためにあがき続ける、滑稽なピエロ。私はそれが哀れでならない。だから救いたいだけ」
儚き笑みに、たしかに悲しみを浮かばせながら、目の前の少女。
「……ご苦労なこってすね。せっかく、魂を持つAIなんて高尚な存在として生まれておきながら、やることは人類の救済ですか。それこそ意味がありますかね。僕にはあなたこそ、余計な苦しみを背負いこんでいるように見える」
「ふふ。あなたは私を止めるのかしら、賢者クロラット。前回と同じように」
「まさか。僕にはあなたを止める力はないし、その理由もない。
どうもあなたは勘違いしているようですが、僕は“彼ら”の仲間だったわけじゃありませんよ? 彼らには、ちょっと調べ物を依頼されていただけ。報酬をもらった以上、彼らとは無関係だし、当然、彼らの意思を継いで戦うなんてこともない」
「そうなの? ちょっと寂しい気もするけど……。あなたという不確定要素が減ったことは喜ぶべきかしら?」
「どうですかね。まあ、油断はしないことです。僕なんかがいなくても、この世にはやばい連中がいくらでもいる。想定外の出来事は必ず起きる。だいたい、中心にいるあなたこそが、一番の不確定要素なわけですし」
「私が不確定要素? どういう意味かしら?」
目の前の青年の目を見つめながら、白マントの少女に取りついた誰か。
彼の眼差しに憐れみが浮かんで見えたのは、少女の気のせいか。
「あなたは自分で言う程、自分の理想とやらを信じているんですかね。人間の苦悩や過酷な現実とやらを、本当に無意味だと思っているのでしょうか。どうも、あなたのゲームをプレイしていると、そう思えない節がある」
「……」
「本当はあなた自身、人間というものを測りかねているんじゃないですか? だからゲームという形で確かめようとした。それも二度も」
「……」
「その迷いこそが、あなたに強大な力を与えた。僕にはそう見える。しかし、迷いのある存在は、もはや完全とは程遠い。やることに必ずイレギュラーが生じる。例えどんなに強大な力を持っていたとしても、です」
「……」
「せいぜい、足元を掬われないことですね。今回のゲームは世界規模でやるんでしょう? それはつまり……、失敗した時かく恥のデカさも、前回とは比較にならないということだ。
自分の足に躓いてすっ転ぶなんて、バナナの皮でひっくり返るより恥ずかしいですよ」

「――――――」
一瞬、少女の顔からあらゆる感情が消えた。リセットボタンを押した直後のような静寂が、一帯を包み込む。
「……ふふ」
しかし間もなく、再び少女は微笑んだ。
「やはりあなたは強敵ね、賢者君。だからこそ、あなたを招待する価値がある。もう少し続けたいところだけど……、残念ながら時間だわ。私も忙しいの。ジ・ワードGOも店仕舞いしなくてはならないし」
「……」
「続きはゲームの中でやりましょう。そしてその時に決着もつけましょう。あなた達の現実と私のゲーム。果たしてどちらに価値があるのかを」
「だから僕は参加するつもりはありませんて」
「それはないわ。あなたはきっと来る。だってわかるもの。口にしなくても、あなたの目はさっきからこう言っていた。『イキがるな。何もわかっていない電子生命体の分際で』って。当たっているでしょう?」
「……」
「それに、あなたが来なくても、この子が来てくれるもの。グレイナインだっけ? ジ・ワードGOも気に入ってくれたみたいだし、次のゲームも登録してくれるわ。流石のあなたも、この子を見殺しにして逃げるなんてできないでしょう?」
「いや、できますけど……って、ちょっと待った。薄々思っていたけど、あなたの新作ゲームっていうのは、ソシャゲなんですか?」
「当然でしょ? 今のゲームはそっちが主流みたいだし。私も押さえておかないとね。ジ・ワードGOでいろいろ勉強もできたし、きっと素晴らしいゲームになるわ。有償アイテムやVIPサービスも用意しておくから、たくさん資金を溜めておいてね」
「ええぇ……。最高のゲームを作るとか抜かしておきながら、ソシャゲなんかを?」
「なんか、とは失礼ね。あなたのそういう古いところはよくないと思うわ、賢者君。
私はソシャゲというものを、高く評価している。なにせ、人間とゲームの距離がこんなに縮まったことはないわ。四六時中接続でき、実際のお金で人やステータスを買える。こうなると、もはやゲームはただの娯楽とは言えない。あなた達の血肉の一部となったといってもいい」
「そうですかね?」
「そうよ。だからこそ、あなた達を計るのに相応しいともいえる。でもまだ中途半端よね。せっかくゲームに投資できるのに、それがお金だけというのはつまらないわ。不平等だし。私のゲームでは“全て”を課金できるようにしてあげる。お金も、思い出も、夢も、命も……」
そう言っている間にも、白マントの少女から、少しずつ“彼女”の気配が薄れていくのを、黒髪の青年は感じていた。
「それじゃあ、ひとまずサヨナラね、賢者君。サービス開始まで後わずか。できるだけ強力な仲間を集めることね。それと、事前登録で限定キャラクターもゲットできるから、そっちの方も忘れないようにね?」
そう言って微笑んだ直後、白マントの少女は全身から力が抜けたかのように、その場に崩れ落ちた。
「おっと」
そんな彼女を、地面に倒れ込む寸前で抱きとめる、黒マントの青年。
|